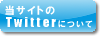「安心・安全な街づくり」のため「安心・安全な運転」を
令和2年度「青パトセミナー」を開催
令和2年10月7日(水)、世田谷区の警視庁交通安全教育センターで『令和2年度青パトセミナー』が開催されました。日頃から青色回転灯を装備する自動車(通称青パト)による自主防犯パトロールを行っている防犯ボランティアの方たちをはじめ、行政職員や警備員など29名と14台の青パトが参加しました。




冒頭、本セミナーの主催者である東京都都民安全推進本部 総合推進部 都民安全推進課安全・安心まちづくり担当の松井課長が挨拶に立ちました。
「私が所属している東京都都民安全推進本部は、遡ること平成15年、石原慎太郎都知事の時代に緊急治安対策本部という組織として発足しました。前年の平成14年の刑法犯認知件数が戦後最悪の数値を更新したことを受けて発足した組織であり、当時は、警察の力だけではなく、自治体や市民の皆様のお力もお借りして治安対策が必要な時代でした。」
それから17年。都内の刑法犯認知件数は戦後最悪の数値を更新した平成14年の3分の1程度にまで減少しました。そうすることができたのも、警察や自治体だけでなく市民の皆様の力が結集したからこそ。
「平成15年当時、都内の防犯ボランティア団体の数は150程度でした。それが今や3800近くまで増え、およそ800台の青パトも登録されています。青パトには少人数で広範囲にパトロールができるという特徴があるほか、ドライブレコーダーを青パトに搭載すれば、“動く防犯カメラ”としても機能するため、今後もさらなる活躍を期待しています」
――と、青パトの可能性と将来性についても触れました。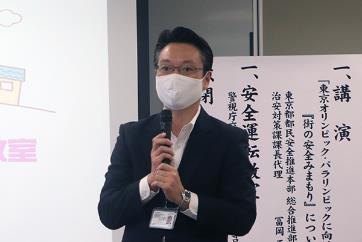 続いて、『うさぎママのパトロール教室』を主宰する安全インストラクターの武田信彦さんによる、『防犯ボランティアが育む! 地域の安全と人々の絆』と題された講義。
続いて、『うさぎママのパトロール教室』を主宰する安全インストラクターの武田信彦さんによる、『防犯ボランティアが育む! 地域の安全と人々の絆』と題された講義。
学生時代に国際的な犯罪防止NPOに参加し、主に渋谷や池袋といった繫華街での防犯活動を経て「市民防犯」を提唱する講師として活動する武田さんは、自らの経験を交えつつ「一般市民ができる防犯のあり方」を話します。
「私が活動に参加した頃は『防犯ボランティア』という言葉すら存在していませんでした。市民による防犯活動がなかなか理解されず、誤解されることも多々ありました。ところが今では、地域のみなさんのみならず、学生たちも地域の防犯に関わるようになっています。最近、私が講師を務める講座に、なんと中学生が参加していました。見守られている立場である中学生が、身守る側として参加しているのです。地域のみなさんが育んだ見守りや助け合いの輪が広がり、世代を超えてバトンが引き継がれていると感じます」
防犯ボランティアのあり方についても、ちょっと意外な話をしてくれます。
「防犯パトロールの最も理想的なあり方は、“何も起きない”ということ。徒歩によるパトロールにしろ、青パトによるパトロールにしろ、街を見守る中で、何もトラブルがないことが一番。事故や犯罪を防ぐために活動しているのですから」
一般市民が行う「市民防犯」は、笑顔やあいさつが重要であると武田さんは強調します。防犯ボランティアが担うべきことは、いわば“間接的な防犯”であって、犯罪が起きにくい環境をつくること。一方、力や権限の行使が伴う“直接的な防犯”は行えない、というのがその理由です。もし、一般市民では対応できない状況になったら、警察や自治体等へお願いするというわけです。
「防犯ボランティアは、犯罪や非行と戦う活動ではありません。笑顔やあいさつの見守りをとおして、人々が緩やかにつながり合う雰囲気こそが犯罪が起きにくい環境となるのです。そして、万が一の時に助け合う力も育まれていきます」
ちなみに、防犯活動という善意の行動であっても、行きすぎたことがあれば違法行為やトラブルになるケースもあります。その点にも武田さんは警鐘を鳴らしているのです。
武田さんが考える防犯ボランティアが目指すべきポイントは、次の2点。
・犯罪が起きにくい雰囲気・環境づくり
・助け合いの環境づくり
加えて、車両でのパトロールの場合には、「車に乗っている」という物理的・心理的な隔たりがあるため、人々とのコミュニケーションが取りづらい面があるとも指摘します。
「安全運転は大前提ですが、さらに優しい運転を心がけ、地域のみなさんや子どもたちの安心感を高めることも重要です。また、ひとりでも多くの人に青パトの取り組みを伝える努力も忘れずに」と武田さんが講義を締めくくると、参加者からは大きな拍手が起こりました。
「私が所属している東京都都民安全推進本部は、遡ること平成15年、石原慎太郎都知事の時代に緊急治安対策本部という組織として発足しました。前年の平成14年の刑法犯認知件数が戦後最悪の数値を更新したことを受けて発足した組織であり、当時は、警察の力だけではなく、自治体や市民の皆様のお力もお借りして治安対策が必要な時代でした。」
それから17年。都内の刑法犯認知件数は戦後最悪の数値を更新した平成14年の3分の1程度にまで減少しました。そうすることができたのも、警察や自治体だけでなく市民の皆様の力が結集したからこそ。
「平成15年当時、都内の防犯ボランティア団体の数は150程度でした。それが今や3800近くまで増え、およそ800台の青パトも登録されています。青パトには少人数で広範囲にパトロールができるという特徴があるほか、ドライブレコーダーを青パトに搭載すれば、“動く防犯カメラ”としても機能するため、今後もさらなる活躍を期待しています」
――と、青パトの可能性と将来性についても触れました。
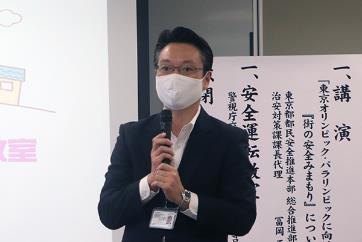
東京都都民安全推進本部 総合推進部 都民安全推進課 松井課長
学生時代に国際的な犯罪防止NPOに参加し、主に渋谷や池袋といった繫華街での防犯活動を経て「市民防犯」を提唱する講師として活動する武田さんは、自らの経験を交えつつ「一般市民ができる防犯のあり方」を話します。
「私が活動に参加した頃は『防犯ボランティア』という言葉すら存在していませんでした。市民による防犯活動がなかなか理解されず、誤解されることも多々ありました。ところが今では、地域のみなさんのみならず、学生たちも地域の防犯に関わるようになっています。最近、私が講師を務める講座に、なんと中学生が参加していました。見守られている立場である中学生が、身守る側として参加しているのです。地域のみなさんが育んだ見守りや助け合いの輪が広がり、世代を超えてバトンが引き継がれていると感じます」
防犯ボランティアのあり方についても、ちょっと意外な話をしてくれます。
「防犯パトロールの最も理想的なあり方は、“何も起きない”ということ。徒歩によるパトロールにしろ、青パトによるパトロールにしろ、街を見守る中で、何もトラブルがないことが一番。事故や犯罪を防ぐために活動しているのですから」
一般市民が行う「市民防犯」は、笑顔やあいさつが重要であると武田さんは強調します。防犯ボランティアが担うべきことは、いわば“間接的な防犯”であって、犯罪が起きにくい環境をつくること。一方、力や権限の行使が伴う“直接的な防犯”は行えない、というのがその理由です。もし、一般市民では対応できない状況になったら、警察や自治体等へお願いするというわけです。
「防犯ボランティアは、犯罪や非行と戦う活動ではありません。笑顔やあいさつの見守りをとおして、人々が緩やかにつながり合う雰囲気こそが犯罪が起きにくい環境となるのです。そして、万が一の時に助け合う力も育まれていきます」
ちなみに、防犯活動という善意の行動であっても、行きすぎたことがあれば違法行為やトラブルになるケースもあります。その点にも武田さんは警鐘を鳴らしているのです。
武田さんが考える防犯ボランティアが目指すべきポイントは、次の2点。
・犯罪が起きにくい雰囲気・環境づくり
・助け合いの環境づくり
加えて、車両でのパトロールの場合には、「車に乗っている」という物理的・心理的な隔たりがあるため、人々とのコミュニケーションが取りづらい面があるとも指摘します。
「安全運転は大前提ですが、さらに優しい運転を心がけ、地域のみなさんや子どもたちの安心感を高めることも重要です。また、ひとりでも多くの人に青パトの取り組みを伝える努力も忘れずに」と武田さんが講義を締めくくると、参加者からは大きな拍手が起こりました。
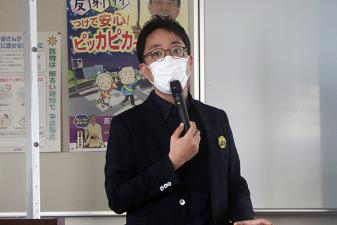
武田 信彦 さん
座学のラストは、東京都都民安全推進本部総合推進部治安対策課の冨岡課長代理から『東京オリンピック・パラリンピックに向けた「街の安全みまもり」について』。残念ながら延期になってしまった東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を控え、地域の防犯・テロ防止における注意点をレクチャーしました。
「テロ事件が起きるのは、人が多く集まる場所。爆弾などの危険物が置かれるのは、見えにくい場所です」
冨岡課長代理は、過去に世界で起きたさまざまなテロ事件の概要を解説しながら、注意すべきポイントを説明します。
不審者なら、「同じ場所を行き来するなど行動が不自然」「人目を気にしながら周囲の様子をうかがっている」「防犯カメラの位置を気にしながら警備員を確認している」など。不審物なら、「発見されないように隠して置いてある」「必要以上に厳重な包装・固定をしている」など。
「防犯パトロールの際に、不審な人や物を見つけたときには、皆さん自身で対応せずに必ず110番してください。その通報が仮に間違いであっても、一向にかまいません。安全であることが確認できればそれで良いのですから」
と、力強い言葉で締めくくりました。
「テロ事件が起きるのは、人が多く集まる場所。爆弾などの危険物が置かれるのは、見えにくい場所です」
冨岡課長代理は、過去に世界で起きたさまざまなテロ事件の概要を解説しながら、注意すべきポイントを説明します。
不審者なら、「同じ場所を行き来するなど行動が不自然」「人目を気にしながら周囲の様子をうかがっている」「防犯カメラの位置を気にしながら警備員を確認している」など。不審物なら、「発見されないように隠して置いてある」「必要以上に厳重な包装・固定をしている」など。
「防犯パトロールの際に、不審な人や物を見つけたときには、皆さん自身で対応せずに必ず110番してください。その通報が仮に間違いであっても、一向にかまいません。安全であることが確認できればそれで良いのですから」
と、力強い言葉で締めくくりました。
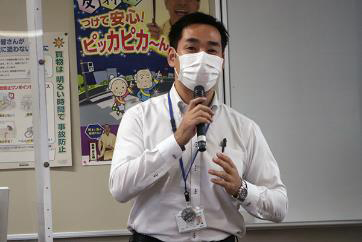
東京都都民安全推進本部 総合推進部 治安対策課 冨岡課長代理
最終プログラムは本セミナーのメインイベント、自動車教習コースに出て実際に青パトを使用しての走行訓練です。あいにくの天候のなかでしたが、警視庁交通安全教育センターの現役警察官の方の指導のもと、行われました。
「安全・安心なまちづくり」のため、「安全・安心な運転」を求められる青パト、ドライバーが身に付けるべき必要な知識や技術について指導を受けました。
この日行われたのは、「急ブレーキ」と「緊急回避行動」の二項目。どちらも時速40kmから、フルブレーキを掛けたり急ハンドルを切ったりと、普段のパトロールの際には行わない運転動作となります。とはいえ、雨で路面が濡れているなか、さすが普段から街をパトロールしている皆さん、見事な運転を披露してくれていました。
「安全・安心なまちづくり」のため、「安全・安心な運転」を求められる青パト、ドライバーが身に付けるべき必要な知識や技術について指導を受けました。
この日行われたのは、「急ブレーキ」と「緊急回避行動」の二項目。どちらも時速40kmから、フルブレーキを掛けたり急ハンドルを切ったりと、普段のパトロールの際には行わない運転動作となります。とはいえ、雨で路面が濡れているなか、さすが普段から街をパトロールしている皆さん、見事な運転を披露してくれていました。


訓練開始前には、しっかりと準備運動&事前説明を!

直前に切り替わる信号に俊敏に反応

普段はなかなか見られない青パトの車列
このページの関連カテゴリー