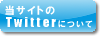平成27年度 地域安全マップ指導者講習会を開催しました!! |
東京都は、子供の犯罪被害防止能力の向上を目指し、平成17年度から犯罪機会論に基づく「地域安全マップづくり」の指導者育成に取り組んでいます。都が推奨する地域安全マップづくりとは、子供自身が「安全な場所や危険な場所」を景色を見て判断できるようにするものであり、これまでの不審者マップや犯罪発生マップとは異なります。このため考案者の小宮教授(立正大学)から直接、指導方法を学ぶ講習会を開催し、理解を深めていただいています。
今年度は、7,8月に町田市教育センター・江東区文化センター・国分寺市ひかりプラザにて計3回の指導者講習会を開催し225名の方に参加していただきました。小宮教授や小宮ゼミの学生が各班のマップづくりをサポートし、和やかな雰囲気の中で進行しました。

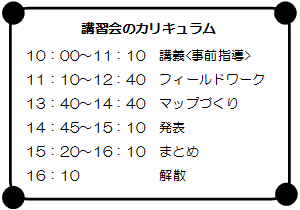
今年度は、7,8月に町田市教育センター・江東区文化センター・国分寺市ひかりプラザにて計3回の指導者講習会を開催し225名の方に参加していただきました。小宮教授や小宮ゼミの学生が各班のマップづくりをサポートし、和やかな雰囲気の中で進行しました。

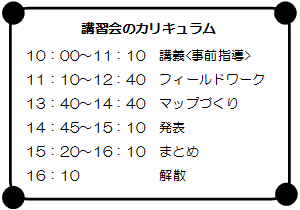
講義 <事前指導>
小宮教授は映像を用いて犯罪機会論を説明。犯罪機会論とは、犯罪を行う“人”ではなく、“場所”に着目し、そうした場所には近づかないことで犯罪の発生を抑止しようとする考え方です。そして、「犯罪者は「入りやすい」「見えにくい」場所を好む。子供がそうした場所の景色を見て、判断できるように指導することが大切」と力説され、過去に子供が被害にあった現場の解説と、子供への指導方法を説明されました。
講義の最後には、小宮先生から防犯クイズが出題され、理解度を高めました。
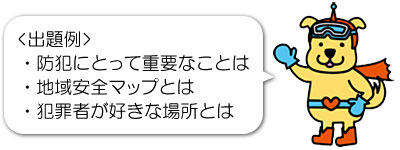
講義の最後には、小宮先生から防犯クイズが出題され、理解度を高めました。
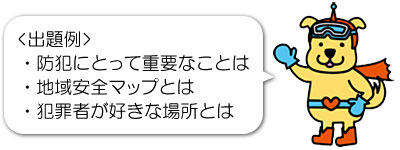
フィールドワーク <まち歩き>
事前指導の後、各グループに分かれてフィールドワークに出発です。
受講者一人ひとりに、班長、副班長、写真係、地図係、インタビュー係などの役割が与えられます。道行く先々では「この場所はどうかな」と立ち止まり意見交換。講義で学んだ2つのキーワード「入りやすい」「見えにくい」をもとに、危険な場所や安全な場所を探しました。
マップづくりの目的は「景色解読力」を養うことです。
景色の再現に役立つ写真を適宜撮影し、後でメンバーとの認識の共有に役立てます。また、地域の方へ「この辺には犯罪にあうかもしれない場所はありますか?」とインタビューし、地域の大人と子供とのコミュニケーションづくりの重要性についても学びました。


受講者一人ひとりに、班長、副班長、写真係、地図係、インタビュー係などの役割が与えられます。道行く先々では「この場所はどうかな」と立ち止まり意見交換。講義で学んだ2つのキーワード「入りやすい」「見えにくい」をもとに、危険な場所や安全な場所を探しました。
マップづくりの目的は「景色解読力」を養うことです。
景色の再現に役立つ写真を適宜撮影し、後でメンバーとの認識の共有に役立てます。また、地域の方へ「この辺には犯罪にあうかもしれない場所はありますか?」とインタビューし、地域の大人と子供とのコミュニケーションづくりの重要性についても学びました。


マップづくり

ランチ休憩後は、いよいよマップづくりです。
模造紙に自分たちが歩いたコースをフリーハンドで描きます。精緻な地図は必要ありません。
そして、安全な場所や危険な場所の写真を貼り、マップづくりで最も大切なコメント作成をします。その景色が「なぜ安全、危険」と考えるのか、場所ごとに必ずキーワードを入れて付箋紙に記入します(この過程で景色解読力を定着させます)。
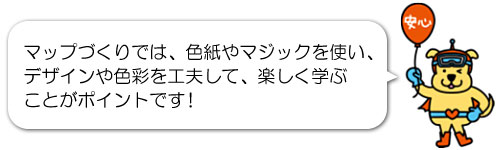
発表
グループごとに、代表者が「入りやすい」「見えにくい」というキーワードを用いて、なぜこの場所を危険と考えたのか。また安全と思ったのか、受講者全員に説明します。


まとめ
 小宮先生による本日のまとめです。
小宮先生による本日のまとめです。「一つの場所で安全と危険が混在する場所もある。安全である理由あるいは危険である理由がそれぞれ正しければ問題なく、子供たちにどちらであるか決めさせる必要はない。景色を見て考えることで、景色解読力は身に付く。そのように意識することがとても大切」とお話しされました。
最後に、「マップは作るが、そのことが目的ではない。」と明言。「子供たちは学校や遊びに行くとき、地図を見ながら歩く訳ではない。その場の景色を見て、安全・危険を判断する能力を育てることが重要」と力説されました。
地域安全マップづくりは、子供たちがそうした能力を身に付けるのに、とても有効な取組です。
受講された皆さんには本講習会で学んだ知識や経験を活かし、学校や児童館で子供の犯罪被害防止能力の向上にお役立ていただければ幸いです。

このページの関連カテゴリー