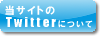学校での危機管理体制づくり
子供を犯罪被害から守るため、日頃の危機管理体制はできていますか?
- 危機管理のねらい
- かけがえのない子供たちの命や安全を守る
- 適切な学校体制を確保し、学校への信頼を守る
校内体制づくり
- 危機意識や危機管理能力の向上
- 日頃からの情報交換や意見交換
- 全教職員が参画した計画づくり、マニュアルづくり
- 防犯や心のケア等に係る研修、訓練
- 児童・生徒への防犯教育、訓練
- 機能する組織体制の整備
- 情報収集と整理、共有
- 正確な伝達、通報、発信
- 記録の累積と整理
- 明確な役割分担と迅速・的確な対応
実践事例
非常通報体制『学校110番』訓練の充実(都立C特別支援学校)
本事例の特色
- 緊急事態を想定した綿密なシナリオ(以下の表1、2)を作成することによって、全教職員が危機意識をもち、 他の教職員の動きを確認しながら訓練することができます。
- 事後に、シナリオと実際の訓練との違いを比較することによって、 次の訓練に生かすことができます。
【シナリオ1】
| 時刻 | 不審者 | 第一発見者 | 校長 | 副校長 | 事務 技能職員 |
生活指導部 | 児童生徒 教員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||
| 10:20 |
|
|
|
|
|
|
|
【シナリオ2】
| 時刻 | 警察 消防 |
学級担任 授業者 |
学部主任 学年主任 |
寄宿舎職員 養護教諭 |
保護者 アドバイザー 教育相談員 |
訓練の発言内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校を取り巻く地域
- ネットワークの構築
- 開かれた学校づくりと信頼関係
- 情報の共有化、率直な意見交換
- 役割分担と連携
- 校長のリーダーシップ
- 行動
- 学校の防犯訓練や研修への参画
- 組織体制への位置付け
- 具体的な対策と行動
実践事例
地域ぐるみのセーフティーネットワーク(D市立E中学校)
本事例の特色
- 中学校区を単位とすることで、学校(園)、家庭、地域、 関係機関のすべてが連携する組織がネットワークできたことです。
- 会合だけでなく、地域パトロールや地域安全マップづくり、防犯講習会の実施等、行動に移す過程で、 相互のコミュニケーションが深まり、「地域ぐるみで子供を守る」ために有効な実践が生まれたことです。
- 学校と地域との信頼関係が深まり、防犯だけでなく学校運営にも支援を得られるようになりました。
中学校区(中学校1校、小学校3校)が、地域との連携を深めた学校安全に関する取組を推進するため、 地域でのネットワークを構築し、情報交換や実践に努めている。
- E中学校区教育推進協議会委員
- 各小・中学校長、幼稚園長、保育園長、各校PTA会長
- 各地区青少年対策委員長、自治会長
- D市の防犯協会会長、消防団長
- 視庁F警察署生活安全課長(防犯係長、少年係長)
- 都立G高等学校にも支援を要請する
- 活動内容
- 学校安全推進委員会の開催:年間5回(情報交換、意見交換等)
- 防犯訓練・防犯教室の実施:保護者や地域住民とともに、不審者侵入時における児童・生徒の避難誘導訓練、小学校非常通報システム訓練
- 防犯講習会の実施:地域に向けての防犯講話、実技研修
- 視察研修:警視庁、交通管制センター、先進校訪問
- 講演会参加:学校安全研究大会等
- 地域安全マップ※の作成:児童・生徒の安全に関する意識調査、地域点検(地域パトロール)、地域安全マップの作成・配布、指導
- 防犯パンフレットの作成:情報収集及びパンフレットの作成・配布、指導
※地域安全マップ活用の留意点(H市学校安全推進委員会)
- できるだけ、家庭内で目立つところに掲示してください。
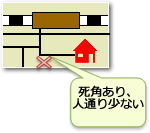
- お子さんとよく遊ぶ公園や通る道路、交差点の様子を実際に確かめてください。
- 近所の「子供110番ハウス」の位置も確かめてください。
- 不審者の出没する場所は、あくまでも目安です。犯罪の方法も様々で巧妙になっています。 いつ、どこで、どのような被害にあうかわかりません。不審者にあった場合は、大声を出す、 近くの家に逃げ込む(学校では、日頃から、不審者にあったときは、 近くの家や「子供110番ハウス」に逃げ込むように指導しています。)、近くの人に助けを求めるとき、 どのような言葉で具体的に話すか、どんな逃げ方をするか等、ご家庭でも話し合っておいてください。 もし、不審者にあったら、程度によらず、警察及び学校にも連絡してください。 一刻も早く「110番通報」してください。
- 何よりも、「自分の身は自分で守る」という意識をお子さん自身がもつことが大切です。 また、家庭及び地域の大人たちが子供たちの安全を考えていこうという意識をもつことが重要です。
実践事例
地域と連携した取組の事例
本事例の特色
- 地域や大人同士の結束力が学校安全につながります。
- まずは、「できる人から、可能な範囲で」行動することです。
- 地域での活動や行事に子供たちを巻き込み、大人が自分たちを見守ってくれていることを実感させたいものです。
- 警察官OB・シルバーポリスの地域巡回パトロール
I市教育委員会は、市内在住警察官OBの方にシルバーポリスとして登録 していただき、学校内の巡回、朝会での児童への呼びかけ等に取組んでいる。 - 防犯ボランティアによる地域パトロール
町会やPTA等が中心となり、通学路での安全誘導、学校周辺巡回、自転 車前籠のステッカー表示等に取り組んでいる。 - 街ぐるみのあいさつ運動
「あいさつのまち○○」をキャッチフレーズとして、街の大人が子供たちに 積極的に声を掛けるとともに、子供たちとともに地域活動を企画している。 - 地域がかかわる安全教育
子供自身が、安全に生活する力を身に付ける安全教育を推進するために、警察や消防署の職員から直接講話等を受けたり、 教員と一緒に「子供110番の家」を訪問して話を聞いたりしている。
このページの関連カテゴリー